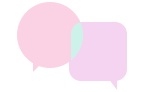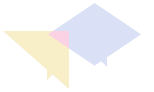生活困窮
「生活困窮」について。番組で紹介した内容や専門家の情報をもとに、理解を深めるために必要な基本をまとめました。
相談窓口・支援団体
生活に困った時の情報・相談窓口
困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障する国の制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります) 厚生労働省のホームページで、制度の概要、お近くの相談・申請窓口の情報を紹介しています。
生活保護制度(厚生労働省) ※NHKサイトを離れます
生活困窮者支援を行う一般社団法人「つくろい東京ファンド」が開発した、webサイト上で生活保護の申請書を作成できるサービス(無料)です。生活保護申請には決まった様式はなく、必要事項さえ記入されていれば申請ができます。 名前や住所(いま寝泊まりをしている地域)、収入についてなど、サイト上で項目に回答していくと、自分で申請書を作ることができます。また、東京23区の福祉事務所で申請する場合には、申請書をサイト上からFAX送信することもできます。
フミダン 生活保護申請 ※NHKサイトを離れます
「扶養照会」をされたくない事情がある方は、厚生労働省の通知内容をもとに、「つくろい東京ファンド」が作った「扶養照会に関する申出書」「申出書添付シート」をダウンロードできます。 申出書をプリントアウト・記入し、添付シートの項目で個別の家族事情にチェックを入れて、生活保護を申請する時に持参し、本人の意思を示すことができます。 厚生労働省は、本人が扶養照会を拒む場合には、「扶養義務履行が期待できない場合」に当たる事情がないかを特に丁寧に聞き取るという運用を求めています。
扶養照会に関する申出書(つくろい東京ファンド) ※NHKサイトを離れます
もし、申出書を持参して窓口に行ったにも関わらず、無理に扶養照会をされるなどの場合は、「つくろい東京ファンド」のホームページから、問い合わせを受け付けています。
問合せフォーム(つくろい東京ファンド) ※NHKサイトを離れます
新型コロナの影響で生活に困っている人のためのメール相談窓口です。リンク先のメールフォームから、相談をすることができます。送信後、スタッフがなるべく早く返信を行い、直接会って詳しく話をうかがい、対応を一緒に考えていきます。(場所・地域・時間によっては時間がかかったり、直接面会ができない場合もあります。)
運営団体:反貧困ネットワーク/新型コロナ災害緊急アクション(運営協力:つくろい東京ファンド)
相談フォーム(新型コロナ災害緊急アクション) ※NHKサイトを離れます
すべての人の健康で文化的な生活を保障するため、福祉事務所の窓口規制をはじめとする生活保護制度の違法な運用の是正など、社会保障制度の整備・充実を図ることを目的として設立された団体です。法律家・実務家・支援者・当事者などで構成されています。 全国の地域ごとに相談を受け付けている支援ネットワークや、生活保護制度に関するQ&Aなども提供しています。
地域ごとの相談先リスト(生活保護問題対策全国会議) ※NHKサイトを離れます
生活保護Q&A(生活保護問題対策全国会議) ※NHKサイトを離れます
国土交通省の住宅セーフティネット制度に登録された住宅の検索ができます。
セーフティネット住宅情報提供システム ※NHKサイトを離れます
住まいを確保するのが難しい方のサポートをしてくれる居住支援法人の一覧を見ることができます。
住宅確保要配慮者居住支援法人について|国土交通省 ※NHKサイトを離れます
NPO法人自殺対策支援センター ライフリンクが運営する「生きる支援の総合検索サイト」です。多重債務や過労、いじめや生活苦など、様々な問題を抱えている人たちが、日本中にある多種多様な「生きるための支援策」の中から、それぞれのニーズに合ったものを迅速かつ的確に探し出せるようになっています。
いのちと暮らしの相談ナビ ※NHKサイトを離れます
24時間どこからかけても無料の電話相談です。自殺予防・DV・性暴力・セクシュアルマイノリティー・被災後の困りごとなどの専門回線が用意されています。外国語でも相談できます。
一般社団法人 社会的包摂サポートセンター|よりそいホットライン ※NHKサイトを離れます
電話 フリーダイヤル:0120-279-338(携帯電話・PHS・公衆電話からもつながります)
岩手県・宮城県・福島県からのフリーダイヤル:0120-279-226(携帯電話・PHS・公衆電話からもつながります)
※電話がかかりにくいことがあります。
FAX:0120-773-776
岩手県、宮城県、福島県からは 0120-375-727
インターネットでの相談「お悩みクラウドMoyatter」も受け付けています。
お悩みクラウドMoyatter ※NHKサイトを離れます
生活に困っている人のアパート入居支援(連帯保証人の提供等)や生活相談・支援、交流サロンの開催などを行っています。
認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい ※NHKサイトを離れます
家がない、お金がない、仕事がないなど、生活に困っている人の相談を社会福祉士が受けて、関係機関と協力しながら一緒に問題解決を行います。生活相談を随時無料で受け付けているほか、住む場所のない人が生活を立て直す時に入居できる、小規模の地域生活サポートホーム(さいたま市内)の運営なども行っています。
NPO法人ほっとポット ※NHKサイトを離れます
貧困問題に取り組む市民団体・労働組合・法律家・学者などのネットワーク。当事者のエンパワーメントや学習会・イベント・ホームページによる発信などを通して、貧困問題の解決に取り組んでいます。
反貧困ネットワーク ※NHKサイトを離れます
※お住まいの市区町村役場の担当部署(福祉課など)、ハローワーク、福祉事務所、社会福祉協議会でも相談を受け付けています。
シングルマザー/ひとり親家庭/子どもの貧困に関する支援団体・相談窓口
日本の子どもの貧困解決を目的として、2010年に設立された個人参加のネットワークです。メーリングリストでの情報発信や相互交流などを中心に、ゆるやかなつながりで運営されています。※直接の相談支援は行っていません。
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク ※NHKサイトを離れます
東京都からの委託を受けて行っている、ひとり親家庭の総合的な支援窓口です。生活相談、就業支援、養育費相談、面会交流支援などを行っています。 相談内容によって対応拠点が違うため、詳しくはホームページをご覧ください。
東京都ひとり親家庭支援センター はあと ※NHKサイトを離れます
シングルマザーが子どもとともに生きやすい社会、暮らしを求めて、情報交換・相互援助、交流等の活動を行っています。
認定NPO法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ ※NHKサイトを離れます
見えにくい子どもの貧困を明らかにするために、子どもや家庭の生活を調査し、子ども・親・周りのおとなをサポートしています。困窮した家庭の子どものおやつ支援なども行っています。
認定NPO法人 CPAO(しーぱお) ※NHKサイトを離れます
全国の子ども食堂の検索ができます。場所によってフードパントリーや学習支援等を行っています。
こども食堂ネットワーク ※NHKサイトを離れます
学習支援
受験や進学に困難を抱える高校生などへの応援給付金や合宿キャンプなどの活動のほか、各地の支援団体を支える活動、子どもの貧困に関する調査や提言も行っています。
子どもの貧困対策センター 公益財団法人 あすのば ※NHKサイトを離れます
首都圏と宮城県で困窮家庭の子どもたちへ無料の学習支援や体験活動を提供しています。 また、コロナ禍で困窮している全国の子育て家庭への様々な支援も始めています。
認定NPO キッズドア ※NHKサイトを離れます
「キッカケプログラム」では、無償の奨学パソコン(レンタルPC・Wi-Fiなど)付きオンライン教育支援などを行っています。生活に関する相談もできる伴走型の支援です。
キッカケプログラム ※NHKサイトを離れます
外国につながりのある子ども・若者たちへの日本語学習支援(対面、オンライン)や居場所支援を実施しています。高校進学のためのプログラムや、生活や仕事に必要な日本語の学習支援も行っています。
YSC Global School ※NHKサイトを離れます
大阪・ミナミで開かれている、外国ルーツを持つ子どものための学習教室です。小学生、中学生、高校生が対象です。
Minami子ども教室 ※NHKサイトを離れます
電話:06-6711-7601(コリアNGOセンター内)
非正規雇用・ブラック企業・過労死など「労働」に関する支援団体・相談窓口
労働相談を中心に、若者の「働くこと」に関する問題に取り組んでいます。残業代、有給休暇、解雇、労災など、さまざまな労働相談を受けつけています。詳しくはホームページをご覧ください。
NPO法人 POSSE ※NHKサイトを離れます
パート、アルバイト、派遣、契約、正社員など、どんな職業・働き方でも、誰でも一人でも入れる若者のための労働組合です。「解雇された」「休みがない」「残業代が出ない」など、仕事をめぐる悩みやトラブルを、同じ境遇の人々と一緒に解決していくための組織です。詳しくはホームページをご覧ください。
首都圏青年ユニオン ※NHKサイトを離れます
ブラック企業問題に対応するため、全国各地の若手弁護士を中心に結成された弁護団。長時間労働、残業代不払い、パワハラなど広く相談を受けつけています。 ホームページには、各地域の相談窓口も掲載されています。
ブラック企業被害対策弁護団 ※NHKサイトを離れます
労働問題や貧困対策に取り組むNPO、大学教授、弁護士、労働組合関係者など、各分野の専門家が力を合わせて発足したプロジェクトです。ブラック企業問題に関する情報や対策方法などの提供を行っています。
ブラック企業対策プロジェクト ※NHKサイトを離れます
労働問題を専門に扱う全国の弁護士によって組織された団体です。ホームページに各都道府県の法律相談窓口が掲載されています。
日本労働弁護団 ※NHKサイトを離れます
全国ネットワーク 過労死弁護団全国連絡会議事務局が行っている相談窓口です。業務上の過労やストレスが原因で発病した結果、死亡したり重度の障害を負ったりした場合について、労災補償の相談を行っています。
過労死110番 全国ネットワーク ※NHKサイトを離れます
過労死で家族を亡くした人たちの当事者会です。全国各地で活動しています。
全国過労死を考える家族の会 ※NHKサイトを離れます
多重債務で悩んでいる方へ
都道府県や市町村の担当窓口、全国の弁護士会、司法書士会、財務局など各相談窓口の連絡先が掲載されています。
金融庁|多重債務についての相談窓口 ※NHKサイトを離れます
多重債務者を生まない社会を目指して、各自治体に対して多重債務対策を指導したり、さまざまな宣言や決議を行ったりしています。ホームページには、全国各地の被害者の会、相談窓口の一覧が掲載されています。
全国クレサラ・生活再建問題対策協議会 ※NHKサイトを離れます
奨学金の返済で悩んでいる方へ
奨学金返済に悩む人の救済・相談活動を行っています。
奨学金問題対策全国会議 ※NHKサイトを離れます
民間の支援団体等については、番組の取材先を中心に掲載しています
「生活困窮」に関する
みんなの投稿
「住まいを失う不安」 あなたは抱えていませんか?
どうにもならない、、かな、、
桃田 / 佐賀県 / 女性 / 50代 / その他
今のままでは、確実に住まいを失います。 20代独身のときから、家族の問題でアパートに一人暮らしでした。 30後半で結婚しても、夫との生活...
今年9月からホームレスです。
ダイ / 神奈川県 / 男性 / 30代 /
3年前に職を失い、病の後遺症があり職がみつかりません。また、実家に生活費を入れ切り詰めて住まわせてもらってますが、姉夫婦と同居し両親からは邪...
非正規雇用の悩み
公立中学校時間講師と市役所兼務(会計年度任用)
HANAちゃん / 千葉県 / 女性 / 40代 / その他
中学校統合までの間に合わせ職員に過ぎない。朝の職員打ち合わせや、職員会議の参加はない。研修の場もない。私の免許は中学校 免許のない職員が技術...
正規雇用の言い分
まー / 埼玉県 / 女性 / 50代 / そのほか
正規雇用です。6/18の放送を見て、正規雇用でいることを申し訳なく感じる内容でした。出演者の女性がワークシェアリングについて話されていました...